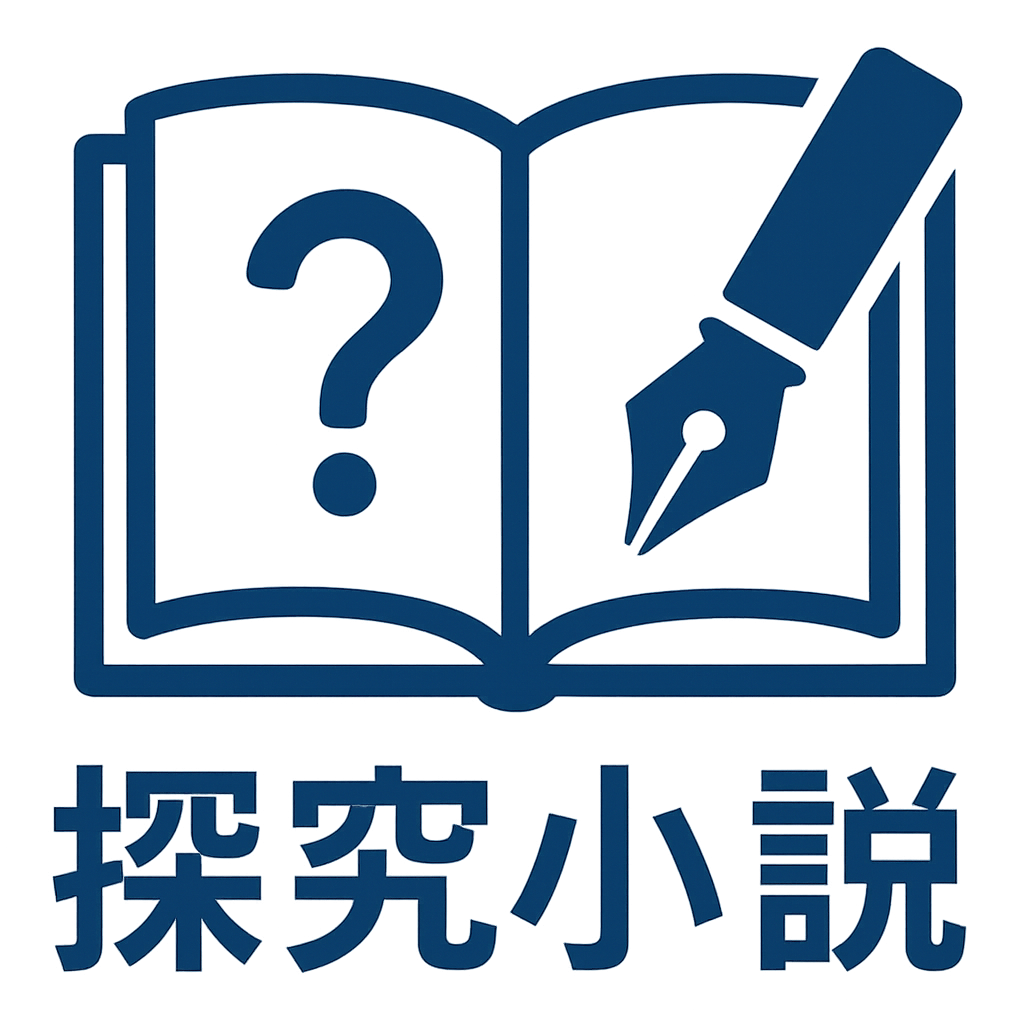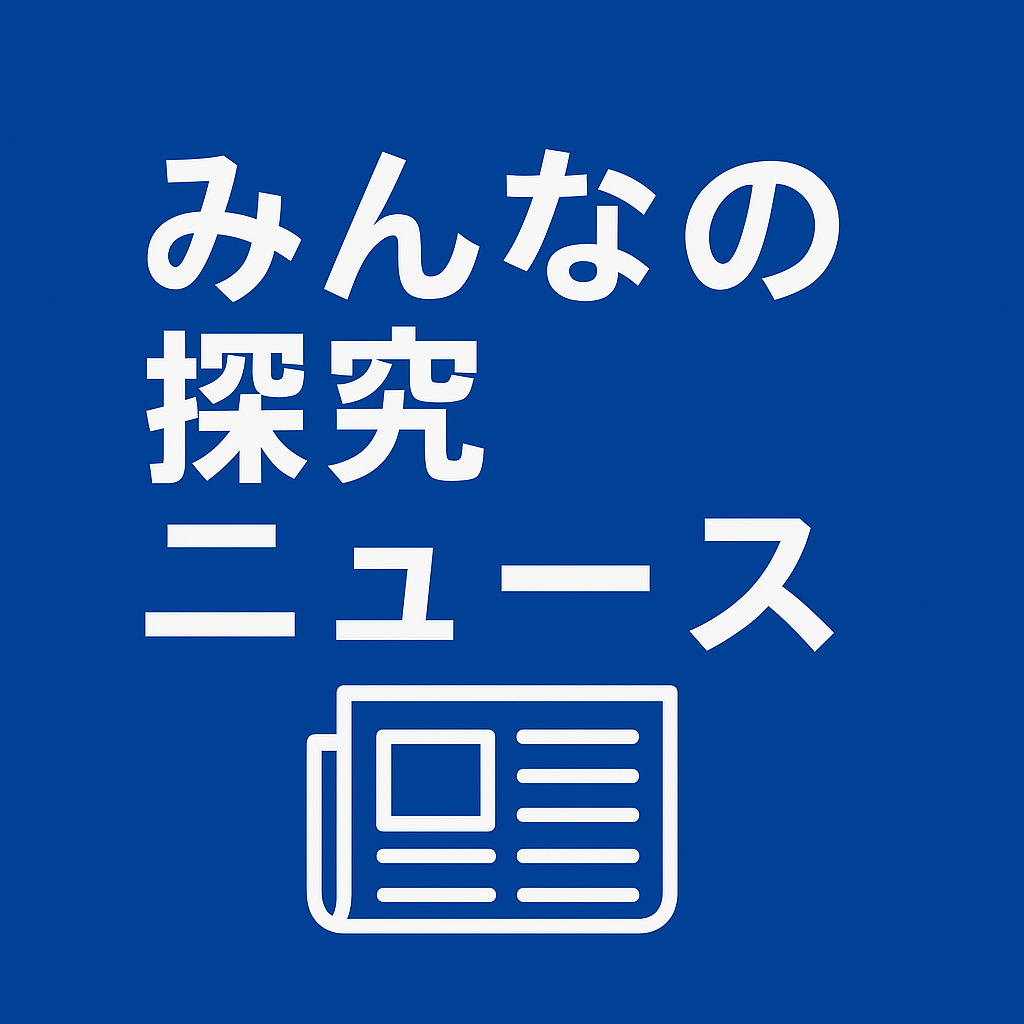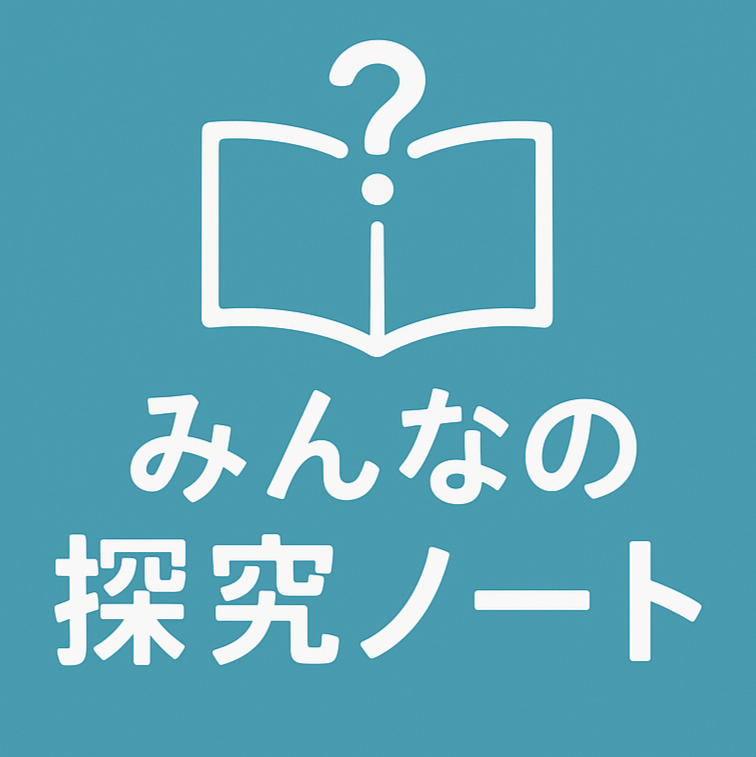市川三郷町 湖と火と紙と石、水と食と湯が響き合う学びの里
峡南にひらける“小宇宙”
甲府盆地の南、富士川と笛吹川に抱かれた市川三郷町。2005年に市川大門町・三珠町・六郷町が合併して誕生したこの町は、湖や火、紙や石、そして水と食と湯が織り重なる“小宇宙”のような地域です。ここを歩くことは、単なる観光を超えて「人と自然がどう共生してきたか」を学ぶ探究の旅になります。
四尾連湖 ― 湖に宿る伝説と静けさ
山あいに浮かぶ小さな湖、四尾連湖(しびれこ)。湖の名には「かつて四匹の大蛇が住んでいた」という伝説が残り、水面に映る空と森が神秘性を際立たせます。湖畔ではキャンプやカヌーが人気ですが、ただ佇むだけでも、日常が遠ざかり、自然の物語に抱かれる時間が流れます。ここでは「自然の物語は、現代人の心にどんな余白を与えるのか」という問いが浮かびます。
神明の花火 ― 夜空に咲く一瞬の芸術
夏の夜、市川三郷の代名詞「神明の花火大会」が開かれます。2万発を超える大輪が山々に響き、光と音が町を包み込みます。花火は、江戸から続く職人の技の結晶でありながら、一瞬で消え去る芸術。そのはかなさは「なぜ人は、消えると知りながら火の花を追い続けるのか」という哲学的な問いを残します。
和紙と印章 ― 紙と石に刻まれる時間
市川大門の「西嶋和紙」は、障子や襖紙として武将の時代から人々の暮らしを支えてきました。清冽な水で漉かれた紙は、光を柔らかく透かし、静かな存在感を放ちます。
一方、旧六郷町は「印章の里」として名高く、水晶やメノウを素材とした石のはんこづくりが発展しました。石を彫る音、水で冷やしながら刻む手の感覚。それは実用品を超えて「小さな彫刻芸術」と呼ぶべきものです。はんこ祭りや印章供養祭が今も続くのは、道具を超えて文化として根づいている証でしょう。
水の町 ― 清流が育む文化
市川三郷町を語るとき、忘れてはならないのが「水」です。山から湧く清水は印章の研磨に欠かせず、和紙を白く仕上げ、農業を潤してきました。町を歩くと今も水路や共同水場の名残が見られ、人々が水を大切に暮らしてきたことが伝わります。「豊かな水が生んだ文化や産業を、これからどう守るのか」――それがこの町に投げかけられた永遠の問いです。
食の恵み ― 果樹と野菜、保存食の知恵
夏には桃やぶどう、甘さ抜群のとうもろこし「甘々娘」が並び、冬には長さ80cmを超える大塚にんじんが収穫されます。さらに「甲州小梅」は保存食や加工品として地域の食文化に根づいてきました。これらの味覚はただの農産物ではなく、季節ごとの暮らしのリズムを刻むものです。「旬の食文化は、人の記憶や地域の絆をどう紡ぐのか」――その答えは食卓に広がっています。
みたまの湯 ― 夜景と温泉が重なる場所
高台に湧く温泉「みたまの湯」は、甲府盆地の夜景を望む絶景の湯として知られます。灯りが湯けむりに揺らめき、星空と混じり合う光景は、天空と地上がひとつになったようです。身体を癒やす湯と、心をほどく眺め。ここでは「癒やしとは特別な贅沢か、それとも生きるための日常か」という問いが浮かびます。
歴史とエネルギー ― 古墳群と水力発電
町内には古墳群が点在し、古代からこの地に人が根を下ろしてきた歴史を語っています。一方、富士川水系を利用した小規模な水力発電は近代から現在に至るまで町を支えてきました。古代の墳墓と現代の発電所――時間も目的も異なる二つの存在が教えてくれるのは「人は常に水と大地に生かされ続けてきた」という普遍の事実です。
結び ― 小さな町に大きな問い
四尾連湖の静けさ、神明の花火の輝き、和紙とはんこの手仕事、水の流れと食の恵み、夜景温泉の癒やし、古墳と発電が語る時間の重なり。市川三郷町は、その一つひとつが問いかけとなり、訪れる人に考えるきっかけを与えてくれます。
この町を歩くと、自然と人、伝統と未来、日常と非日常が交差する瞬間に出会えるのです。探究トラベルは、市川三郷を「学びの場」として私たちに開いてくれます。