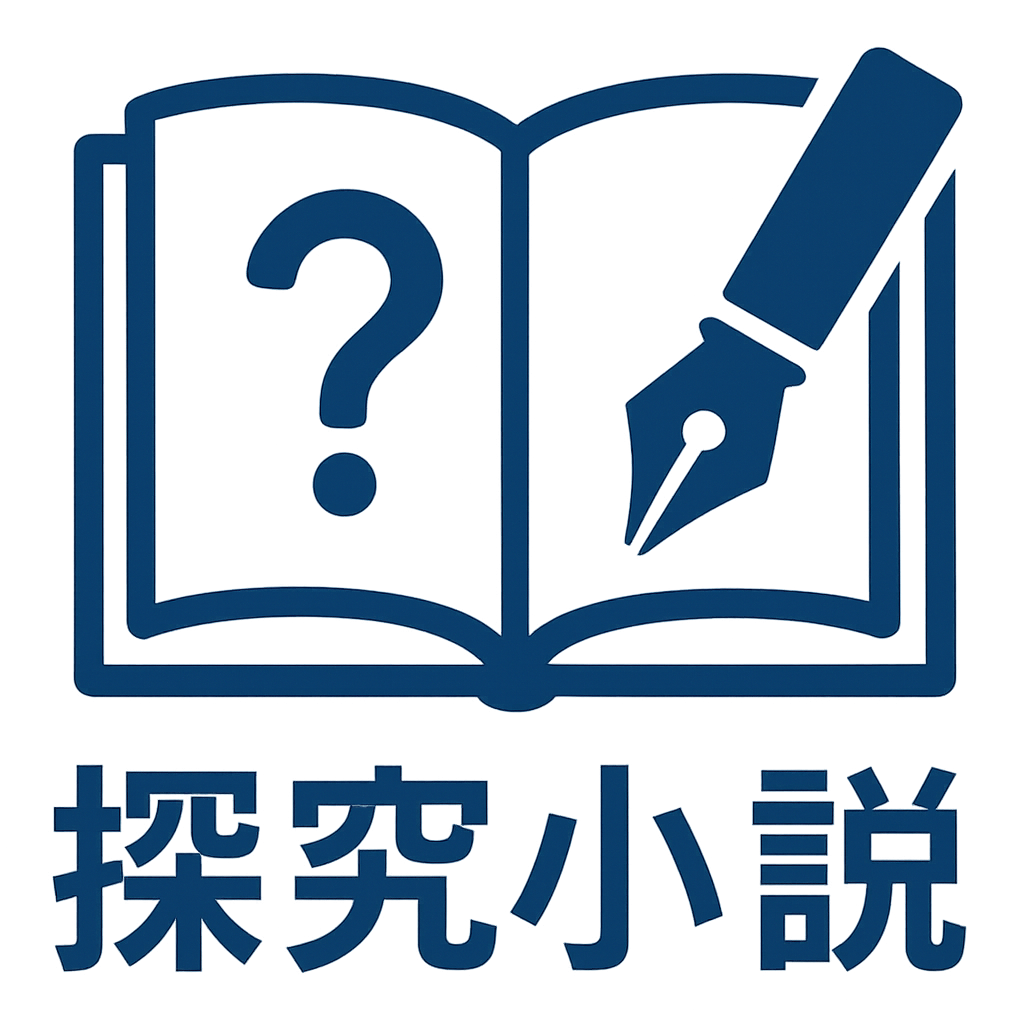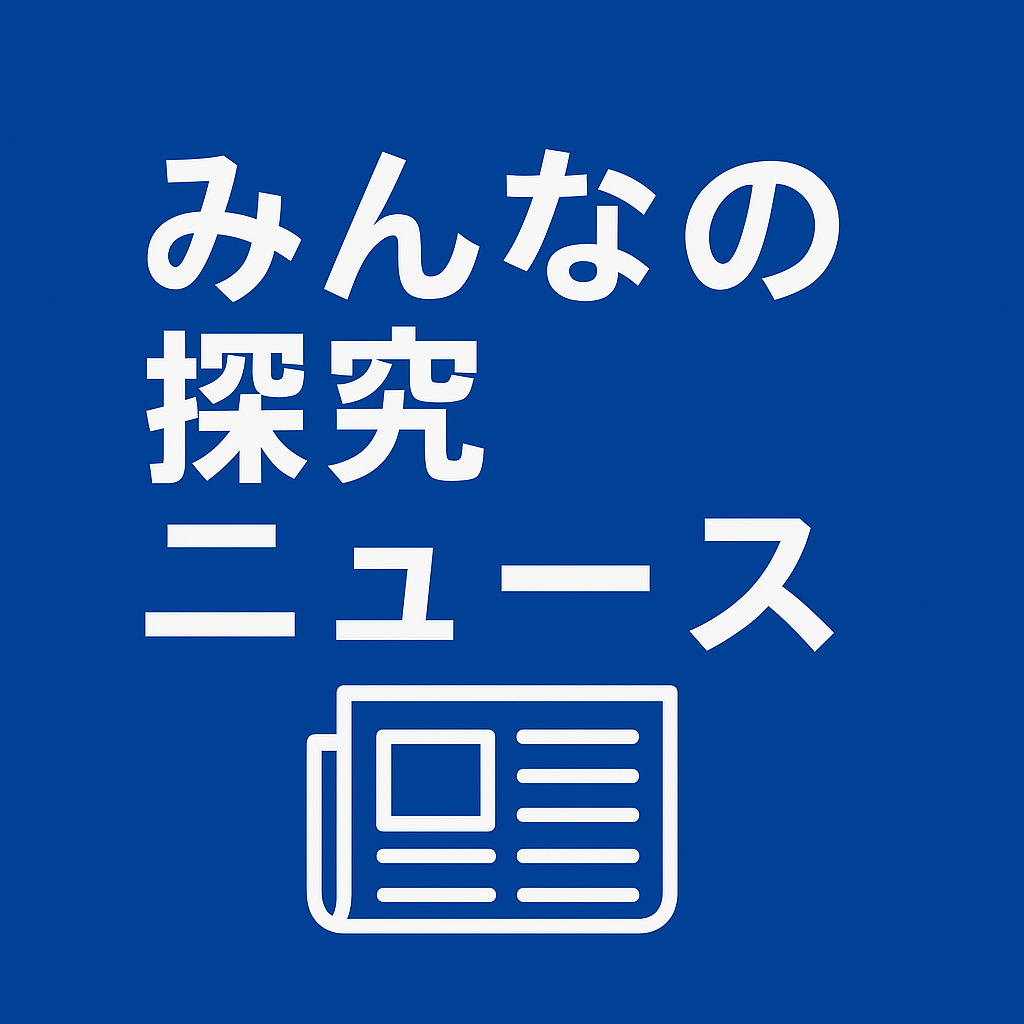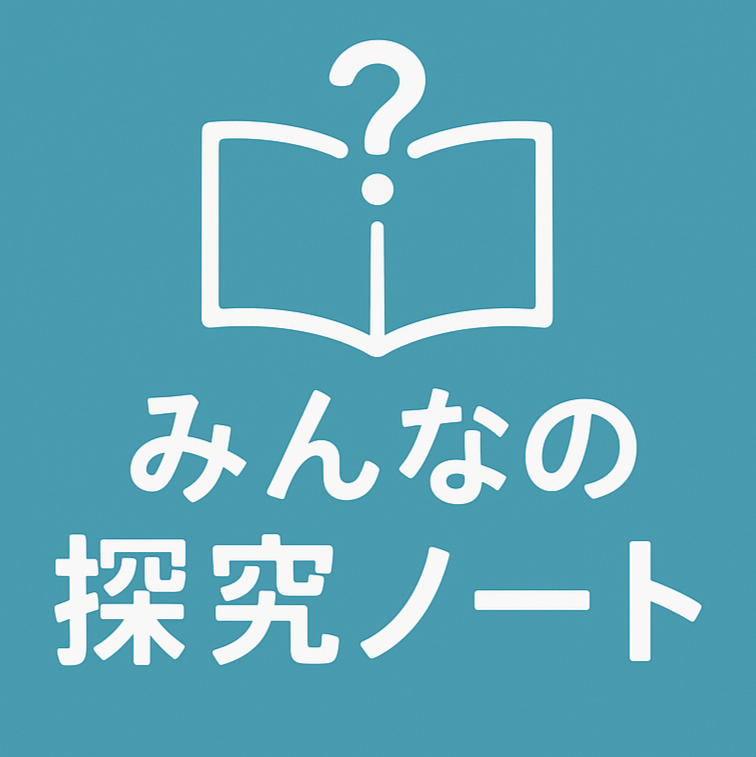関西本線 一筆書きの裏道
1. 一筆書き旅と「二度通過」の壁
鉄道ファンに人気の「一筆書き旅」。同じ区間を二度通らず、ひと筆でぐるりと日本を巡る旅の形です。
ところが、これを実際のきっぷのルールに当てはめると壁にぶつかります。最大の難関は 東海道本線の二度通過。
東京から名古屋・大阪を経て山陰を回り、岡山経由で東京に戻ろうとすると、どうしても東海道を往復してしまうのです。
2. 伯耆大山というT字路
そこで重要になるのが、鳥取県米子市の東にある 伯耆大山(ほうきだいせん)駅。
岡山から北上してきた伯備線はここで尽き、山陰本線に突き当たります。線路はT字に分かれ、東へは鳥取、西へは米子・松江・出雲。伯耆大山は陰陽をつなぐ「結節点」であり、一筆書きを描くには欠かせない支点です。
特急「やくも」は岡山から伯耆大山を経て山陰へ入り、西へ折れて米子・松江へ向かいます。地図の上ではただの小駅でも、陰陽連絡のルートを整える大切な場所なのです。
3. 東海道を避ける知恵 ― 関西本線
問題は、伯耆大山を経由した後にどうやって名古屋・東京へ戻るか。
東海道を使うと二度通過となり、一筆書きのルールから外れてしまいます。
そこで活きるのが 関西本線。名古屋から亀山・奈良を経て大阪へ至るこの路線は、東海道を通らずに中京と関西を結ぶ「裏道」です。
普段はローカル色の強い線区ですが、一筆書き旅では東海道重複を避ける救世主となります。
4. 成立するモデルルート
一例を挙げると、こんな環が描けます。
- 東京 → 金沢(北陸新幹線)
- 金沢 → 敦賀 → 京都 → 鳥取(山陰本線東回り)
- 鳥取 → 伯耆大山(山陰本線)
- 伯耆大山 → 岡山(伯備線)
- 岡山 → 大阪 → 奈良 → 亀山 → 名古屋(関西本線)
- 名古屋 → 東京(東海道新幹線)
このルートなら、
- 東海道は最後に一度きり。
- 京都も一度だけ通過。
- 伯耆大山をしっかり経由しつつ、美しい一筆書きが成立します。
5. 地味な路線が光るとき
関西本線は普段、名古屋〜大阪の主役ルートとは見なされません。列車本数も限られ、決して速くはありません。
しかし一筆書きの視点で見ると、その存在は極めて大きい。東海道の重複を避け、環を完成させるための「知恵の道」なのです。
6. 結び
一筆書き旅には、地図を眺めながらルートを工夫する楽しみがあります。伯耆大山は陰陽をつなぐT字路として旅の骨格を支え、関西本線は重複を避ける裏道として環を成立させる。
一見地味な駅や路線こそが、大きな旅の構図を整える鍵になる――そこに鉄道地理の奥深さがあります。